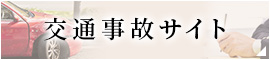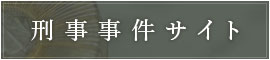ご挨拶
GREETING

「ここまで丁寧に話を聞いてくれる弁護士は初めて」
「アドバイスしてもらって気持ちが楽になりました」
「一人で悩まずにもっと早く相談に来ればよかった」
法律相談の後にこのようなことをよく言われます。
悩みを抱えた生活というのは先の見えない暗闇の
中で手探りで出口を探し求めているような状態です。
そのような人の手を取り進むべき道を指し示して
悩みを解決するお手伝いをするのが弁護士です。
暗闇から抜け出して再び笑顔を取り戻すために。
まずはお気軽に士道法律事務所へご相談ください。
【新規案件の受付制限について】
現在多忙につき新規案件の受付を
『刑事事件の示談交渉』
に限らせていただいております。
その他分野のご相談希望の場合は
他の法律事務所をご検討ください。
当事務所の特徴
FEATURE OF OUR LAW OFFICE

相談内容を弁護士が
丁寧に聴き取ります
大切なのは依頼者と正面から向き合うこと。
どんなことでもお気軽にご相談ください。

相談から事件終結まで
一人の弁護士が対応
相談した弁護士と実際に対応する弁護士が
異なるという事態は絶対に発生しません。

初回の法律相談は
30分or1時間無料
刑事事件は1時間、その他事件は30分。
無料法律相談でしっかりお話を伺います。

事件ごとに明確な
報酬説明書を用意
受任時に弁護士報酬説明書をお渡しします。
不明瞭な費用が発生することはありません。
注力分野
MAJOR FIELD
取扱分野
LEGAL SERVICE
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館201
当事務所からのお知らせ
- 2024.04.08GW休業のお知らせ
- 2024.02.09刑事示談交渉の最新の成立割合
- 2024.01.10新年のご挨拶と2023年のお問い合わせ状況
- 2023.12.15年末年始休業のお知らせ
- 2023.10.02お問い合わせフォームのエラー修復
- 2023.09.29お問い合わせフォームのエラー
- 2023.08.18新規相談の受付制限について
- 2023.07.18夏季休業のお知らせ
- 2023.06.14【刑事事件】のページ更新
- 2023.04.13GW休業のお知らせ
「弁護士のコラム」
- 2024.04.08GW休業のお知らせ
- 2024.02.09刑事示談交渉の最新の成立割合
- 2024.01.10新年のご挨拶と2023年のお問い合わせ状況
- 2023.12.15年末年始休業のお知らせ
- 2023.09.29お問い合わせフォームのエラー
- 2023.09.20【刑事事件】のページ更新
- 2023.08.18新規相談の受付制限について
- 2023.07.18夏季休業のお知らせ
- 2023.06.14【刑事事件】のページ更新
- 2023.04.13GW休業のお知らせ

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-7-1
北ビル1号館201
士道法律事務所(しどうほうりつじむしょ)
営業時間 10:00-18:00